アレルギー外来(詳細)
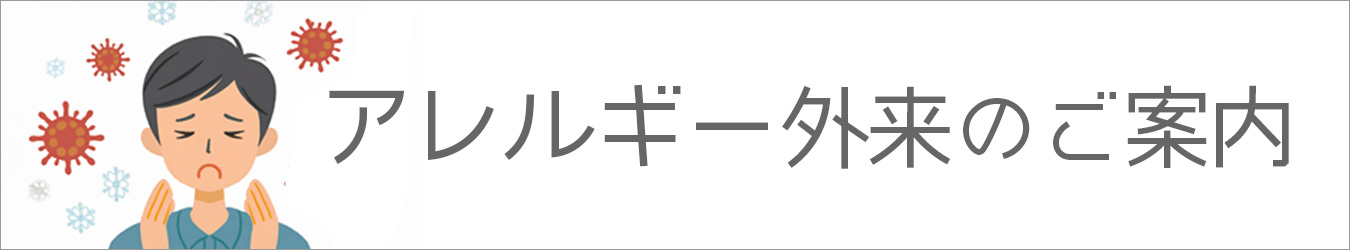
アレルギーの症状
異物(アレルゲン)を体外に洗い流すためにヒスタミンが放出されて、鼻水・涙など分泌が増えたり、顔をはじめとして皮膚がむくんでかゆくなるといった症状がみられます。気管では咳・痰、消化管では腹痛・嘔吐・下痢といった症状が見られます。症状が軽いと風邪や胃腸炎と思われて見逃されていることも多いです。食物アレルギーの場合などに、アナフィラキシーといって全身に次々と症状が広がり、呼吸の苦しさや低血圧を伴ってショック状態に陥り、命を落としうる重篤な場合もあります。
アレルギーは「免疫の暴走」
免疫はその名の通り、疫を免れる(まぬがれる)ためのメカニズムです。アレルギーは、免疫システムが本来無害な物質(花粉、食物、ダニなど)に対して過剰に反応し、身体に害を及ぼす状態を指します。免疫システムは通常、ウイルスや細菌などの病原体から身体を守るために働きますが、アレルギーではこの仕組みが「暴走」し、必要以上に反応してしまう状態。これにより、くしゃみ、皮膚のかゆみ、場合によってはアナフィラキシーショックのような重篤な症状が引き起こされます。
「アレルギー」という言葉は、ギリシャ語の「allos(別の、異なる)」と「ergia(働き、反応)」を組み合わせた造語です。この言葉は、免疫システムが通常とは異なる異常な反応を示すことを表現するために作られました。1906年にオーストリアの小児科医、クレメンス・フォン・ピルケ(Clemens von Pirquet)がこの言葉を初めて提唱しました。
クレメンス医師は、患者が特定の物質(例えば、血清やワクチン)に繰り返し曝露された際に、免疫システムが異常な反応を示すことに気づきました。彼はこれを「免疫の変化した反応状態」と表現し、以下のように述べました。
「アレルギーとは、免疫系が特定の物質に対して通常とは異なる反応を示す状態を指す。この反応は、身体を守るための免疫の働きとは異なり、時には(暴走し)有害な結果をもたらす」
アレルギーの検査
花粉やダニ、食物など、代表的なアレルゲンについては採血でアレルギー体質があるか検査することも可能です。実際のアレルギー体質の有無と、検査結果とが食い違う場合もあります。仮に検査でアレルギー体質がないという結果が出ても、症状に基づいて治療を調節することが大切です。尚、検査をしなくても症状に応じて治療を受けることができます。
アレルギーの治療
成人のアレルギーは完治することは難しいのですが、症状をコントロールして上手に付き合ってゆくことができる病気です。治療に際して重要なのは以下の3点です。
1.原因・誘因の特定と回避
2.早期治療と適切な治療薬の選択
3.全身の合併症に応じた調節
例えば花粉症が悪化すると、鼻づまりでいびきをかき眠りが浅くなり、日中の眠気や集中力低下を生じて生活に支障をきたすことが多いです。また、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目や皮膚の痒みのほかに、咳や頭痛、微熱や倦怠感などを伴うこともあります。咳はのどや胸が痒いような違和感をともなったり、声がかすれたり夜眠れなくなるなど重症になることもあります。このように、目・鼻以外にも全身の治療が必要になることがあります。
専門医に相談を
花粉症の場合でも、市販薬などで症状が落ち着かない場合には自己判断で対処せずに、信頼できるアレルギーの専門医を探して相談してみましょう。専門医ならではの特徴としては、アレルギー体質の採血結果の解釈と対処法の提案や、症状の程度や体質に応じた飲み薬・点眼・点鼻薬の工夫、治療終了のタイミングの提案といったきめ細かな微調整ができること、鼻・眼・皮膚以外にも咳や頭痛などの全身にまたがる症状を総合的に治療することができることなどがあります。
代表的な抗ヒスタミン剤だけでも10種類以上あり、抗ロイコトリエン拮抗薬や点鼻薬などと組み合わせると、治療は数千通りにのぼります。同じ治療費で個人にあったオーダーメイドの治療の提案を受けられることも専門医ならではの特色です。
アレルギーと片頭痛の関係
アレルギー性片頭痛(allergic migraine)という病名があるぐらい、アレルギーと片頭痛は密接に関連しています。『花粉症と頭痛を一緒に治療しましょう』とお伝えすると、つながりが分からずびっくりされる事も多いのですが、実は体の中で両者はつながっています。花粉症で登場したヒスタミンと、片頭痛で重要なセロトニンはどちらも血管の壁に働きかけるオータコイドという物質の仲間でもあります。
花粉症、喘息、アトピーの方に片頭痛が多い事が報告されており、アレルギー性疾患の原因となるヒスタミンが片頭痛に悪影響を及ぼしていると考えられています。アレルギーの薬を頭痛の予防を期待して併用する場合もあります。
2025/07/29

